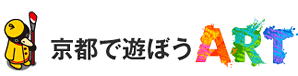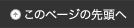橋本関雪とは

橋本関雪(「木蘭」の前にて)
1883(明治16)年、兵庫県坂本村(神戸市中央区)生まれ。幼名を成常、青年となり関一(貫一)と改める。諱を弘という。
関雪は播磨明石藩儒(藩お抱えの儒学者)であった父、海関が藤原兼家の逢坂の関にまつわる故事(*1)から名付けた画号である。
和歌、詩書に親しみ、17歳の頃に画の道を志す。
1903年(明治36年)に竹内栖鳳の主催する画塾「竹杖会」に入り、上村松園、西山翠嶂、小野竹喬、土田麦僊、池田遙邨、西村五雲、金島桂華などの近代日本画の優駿達と交わる。
大正期からは「新南画」(*2)と呼ばれる分野で精力的に作品を発表していたが、昭和期に入ってからは近代の四条派に忠実な写実的な動物画を多く発表し名声を得た。
作品の多くは古典の系譜を踏襲するものであり、彼の作風は総合的に「新古典主義」と分類されている。
文展審査員、帝展審査員を歴任後、1934(昭和9)年に帝室技芸員となる。
1945(昭和20)年没。墓所は生前に別邸として営んだ大津逢坂山にある走井を改めた月心寺につくられる。
代表的作品に「玄猿」「長恨歌」「木蘭」「琵琶行」「唐犬図」「南国」などがある。
*1)平安時代の貴族・藤原兼家が雪降る逢坂の関を越える夢を見、その話を聞いた儒者・歌人の大江匡衡(おおえのまさひら)が「関は関白の関の字、雪は白の字。必ず関白に至り給ふべし」と夢占いをした、という故事。藤原兼家は翌年、関白の宣旨を賜ったという。
*2)中国の南画(文人画)に注目し、そこに近代的な感覚を取り入れた新しい傾向の絵画。
関雪と庭
橋本関雪を語る上で外せないのが「作庭」です。彼は大正初期に行った兵庫県明石の「蟹紅鱸白荘(現・白沙荘)」に続き、京都府銀閣寺畔の自邸「白沙村荘」、そして滋賀県大津の逢坂山に「走井居(現・月心寺)」、最後には兵庫県宝塚に最大の別邸「冬花庵」を造営しています。
関雪自身の記すところに依れば、「庭を造るのも、画を描くのも同じことである。」とされています。
これらの邸宅の庭は、関雪の美意識が強く反映された独特のものであり、彼の作品と同様に古典的手法を踏襲しながらも、上手く新たな要素をミックスしたものです。
幾つもの作庭は生涯に渉って行なわれ続けました。
関雪の作品と京都画壇との関わり
動物画、特に猿が有名な関雪ですが、全体的に見ると非常に幅の広い作風で作品を発表し続けています。若年期には日本的な題材を扱いながら「静御前」、「後醍醐帝」、「片岡山のほとり(聖徳太子の逸話)」などを描きますが、入選を果たせませんでした。
大正に入ってからは、本来の素養であると思われる大陸的な文化を下敷きに、陶淵明や 白居易、李白、杜甫などの漢詩世界を画面に映し始めます。この頃から関雪は急激に評価が高まり、大正末期には没した富岡鉄斎の後継的な役割も果たします。
昭和期からはそれまで敬遠していたフシのある動物画を描き始め、1933(昭和8)年に発表した「玄猿」が、昭和天皇の直讃を受け文部省の買い上げとなりました。このことから関雪はその後「猿の関雪」と呼ばれることになります。
また、余談としては大正期にはその迫力のある描写から「馬の関雪」と呼ばれていました。
動物画を遠ざけていた理由としては、師にあたる竹内栖鳳との確執が原因ではないかと邪推が行なわれているようですが、関雪自身はあまり栖鳳について能動的にアレコレとは言っておらず、反論的に短かな発言が残っているだけでした。この一件については、周囲の者たちがこういう構図を意図的に作り上げていたようにも思われます。
同様に、関雪が一旦京都から東京に赴いたのも、その後東西の画壇から距離を置くのも、同じような理由からであると考えられます。一時期、関雪は同門の画家との交流もできるだけ行なわず、芸術雑誌や新聞紙上では盛んに関雪バッシングが行なわれていました。
しかし、上記「玄猿」の文部省買い上げ以降においてバッシングは止み、関雪はそれまで推挙の無かった美術院会員、帝室技芸員などの大役を歴任することとなります。
関雪の周辺
関雪の父・橋本海関は、博覧強記(はくらんきょうき *3)の人物であったと伝えられており、孫文や鄭考胥、康有為などの大陸文人と交流を持っていたようです。関雪の素養となる大陸的な趣味はこの父から大きな影響を受けています。
また、母のフジは詩歌に通じる才媛であったのですが、関雪が詩歌の世界にも拘っていたのは2歳の頃に生き別れたこの母への恋慕の情であったのかもしれません。
まだ見ぬ母への気持ちは、やがて妻となるヨネ夫人へと向けられました。
ヨネ夫人亡き後、関雪は失意のあまり画を捨てようと考えますが、しばらくの後に画を捨てることは夫人の献身を無にすることだと考え筆をとります。
そこで描き出されたのが「玄猿」でした。
雌雄の黒テナガザルが描かれたその画は当時の論評においても
「夫妻の姿を描いたのではないか」
「漢詩において黒テナガザルの鳴き声は、痛切にして脾に入る悲しい声である」
と語られ、関雪の画業を語る上での揺るぎない名作となったのでした。
*3)広く書物を読み、それらを非常によく記憶していること。知識が豊富なこと。
文:橋本 眞次(白沙村荘 橋本関雪記念館 副館長)
→ 【連載コラム】「白沙村荘の庭から」はこちら
雌雄の黒テナガザルが描かれたその画は当時の論評においても
「夫妻の姿を描いたのではないか」
「漢詩において黒テナガザルの鳴き声は、痛切にして脾に入る悲しい声である」
と語られ、関雪の画業を語る上での揺るぎない名作となったのでした。
*3)広く書物を読み、それらを非常によく記憶していること。知識が豊富なこと。
文:橋本 眞次(白沙村荘 橋本関雪記念館 副館長)
→ 【連載コラム】「白沙村荘の庭から」はこちら