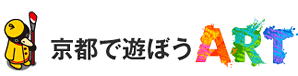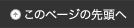竹内栖鳳とは(2)
西の竹内栖鳳 東の横山大観
竹内栖鳳は元治元年(1864)に京都・二条城近くで生まれ、明治・大正・昭和にわたって活躍し,東京の横山大観と共に日本画壇をリードした偉大な画家であった。
13歳(明治10年)の時には、近くに住む四条派の土田英林(つちだ・えいりん/鈴木百年の門人で鳥の画が得意)について絵を習い始めた。そして17歳(同14年)で著名な幸野楳嶺(こうの・ばいれい)に入門を許され、まもなく棲鳳(のちの栖鳳)の画号を師よりいただき、翌年には楳嶺塾の工芸長に任命されるなど、早くからその非凡さを認められた人物である。
21歳(同18年)の時、東本願寺の光勝上人が北越地方の巡錫(じゅんしゃく*1)の際に師・楳嶺を随行させるにあたって、棲鳳も同行させるなど多くの門人の中でも特段の処遇を受けていた。
周囲の期待に違わず棲鳳は、20代後半に入ると各種の博覧会で受賞を重ね、京都の青年画家の中でも抜群の実力を表すことで周囲から認められるようになっていった。
36歳(同33年)の時、京都市と農商務省の依頼で、パリ万国博覧会の視察とヨーロッパの絵画事情の調査を兼ねて7か国の美術行脚を行い、大きな成果を得て帰国した。このころから画号を栖鳳に改め「西洋かぶれ」の悪口も気にすることなく、濃淡のあるセピア調の作品を発表して画人たちや世間を驚かせた。特に明治35年の《獅子》は、今までに見たどのライオンよりも写実的で生きているような迫力で皆を圧倒した。
明治40年(43歳)、第1回文展(文部省美術展覧会)の開催の折、栖鳳は審査員となり、同時に《雨霽(あまばれ)》を出品した。翌年には《飼われたる猿と兎》、明治42年には初めての人物画《アレ夕立に》、44年に《雨》、大正2年(49歳)に《絵になる最初》、大正6年(53歳)に《日稼(ひかせぎ)》を、大正7年(54歳)に《河口》を発表し、翌年文展から帝展に移行するまで、文展の日本画部門を支え続けた。
その後帝展を主催する帝国美術院からも早速会員に任命され、帝展での活躍も期待された。
栖鳳は大正2年(49歳)に帝室技芸員に任命され、また大正13年(60歳)にはフランス国よりレジヨン・ド・ヌール勲章を贈呈され、さらに昭和12年(73歳)の時、第1回文化勲章を横山大観と共に受章し、いよいよ地位も実力も最高の頂に到達した巨匠であった。
栖鳳は円山、四条派の写実をもとにしながらも、狩野派や大和絵の技法も貪欲に取り入れ、近代的な写実主義を実現させていった。しかし栖鳳にはまだまだヨーロッパの写実主義からの遅れを取り戻さねばとの思いがあった。
守旧派からの「西洋かぶれ」との批判も気にすることなく、あえて鵺派(ぬえは)*2 と呼ばせておいて、写生の本質を追求した画人であった。
晩年に至らずとも省筆が巧みで、しかも運筆の妙技は右に出るものはいなかった。
昭和17年(1942)8月23日、栖鳳は77歳の生涯を湯河原で閉じた。日本画壇の巨星が堕ちた寂寥感は、しばらく拭いようのないものであった。
*1 僧が各地をめぐり歩いて教えを広めること
*2 鵺(ぬえ)は、頭が猿で胴体が虎、尻尾が蛇の想像上の怪物。様々な流派の寄せ集めと揶揄する意味でこう呼ばれた。
画室の移り変わり
生家「亀政」時代(誕生~明治20年ころ)
栖鳳の生家は二条城に程近い「亀政」という小料理屋だった。屋号が亀屋で主人の名が政匕。そこで「亀政」が通り名となった。家の近くに町奉行所や二条城があったこともあり、弁当の注文を引き受けるようになって小さな店も繁盛した。そうこうしている間に政匕夫婦に娘・琴(こと)が生まれた。
店が手狭になったので、万延元年(1860)に一家は御池通油小路へ引っ越した。泉水もある庭では川魚が泳いでいた。そんな店にまもなく男子が生まれ、その子は恒吉と名づけた。これが後の竹内栖鳳である。
恒吉は成長していくにつれ、家業を継ぐより絵描きになりたい一心であった。
13歳の時母が亡くなると、10歳年上の姉が母に代わって店を切り回すことになった。
これをいいことに、恒吉は絵描きの道を邁進することになり、その4年後に希望通り、幸野楳嶺の画塾へ入門、雅号「棲風」(後の栖鳳)を得た。
明治19年(22歳)、京都を訪れたフェノロサの講演会に参加した折に「日本画は外国でも受容される実用的な図案を工夫すべきである。」との言葉をいたく感動的に聞いた。栖鳳はフェノロサが外国でも通用する日本画を書けと言っているのだと理解した。
御池「耕漁荘」時代 (明治20年~昭和4年)
フェノロサの講演を聞いた翌年の明治20年8月、栖鳳は西陣織業の高山家の長女奈美と結婚。生家である亀政の筋向いに父親から買ってもらった家に「耕漁荘」と名づけ引っ越した。ここが栖鳳の画室の拠点となり、徐々に弟子も増えるにつけ、居室も画室も少しずつ拡張していった。
「耕漁荘」の名の由来は、「耕漁せずば食わず」の意味で富岡鉄斎が命名したと伝えられている。
南画の大家として活躍した鉄斎は栖鳳の師・楳嶺と親交があったが栖鳳ともいろいろと交流があったので、気に入った中国の漢詩から選んだことだろう。
栖鳳はこの耕漁荘で42年間を過ごし、その間、人生前半期の大部分の作品を制作した。
明治28年に日清戦争が終結すると、鉄道網が拡張・整備され、洋画家たちは頻繁に写生旅行を行うようになった。対して模写が中心の日本画は遅れを取っていた。そこで栖鳳は弟子たちに写生することを奨励した。
また栖鳳は明治30年ころから西洋の近代風景画やターナーについても学んでいた。弟子にはいつも「ただ対象をよく見て写生せよ」というばかりであったが、たびたび「動物を描くなら体臭まで描くように」、「鳥を描くなら鳴声が聞こえるか」と問うた。
何を主題にしても、対象の本性を鮮やかに写し取っているか、またその対象が最も絵になる情景(構図)を写し取っているかを問うたのだ。
だが栖鳳は決して弟子たちに自分の画風を強要はしなかった。
このころ栖鳳は人物画を3点描いている。明治42年(45歳)に《アレ夕立に》、大正2年(49歳)に《絵になる最初》そして大正6年(53歳)に《日稼(ひかせぎ)》である。
これらは栖鳳の代表的な人物画である。
その後もさらに多くの人物画が生み出されることを期待したいところであったが、天女のモデルとなった女性の死がきっかけで、栖鳳はこれを限りに人物画を止めてしまったのは、まことに残念なことであった。
なお耕漁荘は、その後昭和19年に戦時体制のもとで強制疎開のため取り壊されている。
嵯峨「霞中庵」時代(明治45年~)
画業が盛んとなり弟子も多くなるにつれ、栖鳳は個人的な空間が欲くなり、嵯峨に別荘を購入した。その地は旧壬生邸の家屋敷であったが、さらに庵と庭は新しく建てる予定だった。
茶をたて、句を詠み、自然の移ろいを愛でられる風流の空間は、栖鳳自身が設計しあらゆるものまでこだわって作ったものである。
敷地はおよそ3000坪。御池の「耕漁荘」からの移動は列車(山陰線)を使ったらしいが、遊ぶのにも時間のいる時代であった。
このころ栖鳳は弟子の育成にも力を入れていた。明治42年には京都市立絵画専門学校の教授となり、また画塾「竹杖会」を主宰して上村松園、西山翠嶂、西村五雲、土田麦僊、小野竹喬、池田遥邨、橋本関雪、金島桂華など日本画壇に名を残す多くの俊英を育てた。
※現在霞中庵は一般公開はされていない。
高台寺「霞中山房(東山艸堂)」時代 (昭和4年~)
快適で開放的な嵯峨「霞中庵」は多くの招待客を招き入れたが、あまりに景色が良いために栖鳳は画を描く気にならなかった。そこで、高台寺に全面スリガラスの窓にして下界を遮断したもうひとつの別荘を造ることにした。
しかしいざ建設となると栖鳳の意図と設計側がうまくかみ合わず、なかなか思うようにはかどらなかった。
そしてようやく昭和4年、「耕漁荘」と「霞中庵」を折衷したような屋敷、つまり生活空間と別荘空間を折衷した新邸を建てたのである。1300坪の敷地に175坪の建物であった。
この屋敷の庭は泉水はなかったものの、見事な枝垂桜(人丸桜)と藤棚があり、訪問客が驚くに十分なものであった。聞くところによると、この桜は門弟の金島桂華の庭にあったものを、たまたま知らずに栖鳳が所望したことがきっかけらしい。
※現在はイタリア料理店(THE SODOH HIGASHIYAMA/旧ガーデンオリエンタル京都)として利用されている。通常門内には入れないが、利用客には見学も可能。
湯河原「山桃庵」時代(昭和9年~昭和17年)
「霞中山房」(新邸)が落成した年の秋、栖鳳は肺炎にかかり一時床に臥せることになった。しかしその後も、栖鳳は流行性感冒にかかったり、カタル性の肺炎や胃潰瘍、胆石症、栄養障害、神経痛などの病に続けて罹り、ついに医者より気候温暖な土地で療養すべしと忠告された。
そこで人を介して探し当てたのが、熱海に近い湯河原温泉の「天野屋」であった。
この宿は昔は伊藤博文や犬養木堂、夏目漱石などが逗留したこともあって栖鳳は気に入り、しばしば東京の帰りに立ち寄っていた。栖鳳への店側の気配りは目立つほどではなく、さりげないもてなしが心地良かった。
そして主人の好意で、まもなくこの宿の一隅に小さな居室と画室を兼ねた別宅を新築することになった。堂号の「山桃庵(やまももあん)」の山桃は、温かい山地に生える常緑樹で、甘酸っぱく野趣に富んでいるのと、山桃という名前を気に入り名ずけたようである。
栖鳳は湿気の多い高台寺の新邸を存分に使わないまま湯河原での生活が常態化していった。やがて昭和17年8月23日、肺炎のため「山桃庵」で77年の生涯を静かに閉じたのであった。
※「天野屋旅館」はその後登録有形文化財となったが、平成20年に売却先が建物すべてを解体したため、現在その姿を見ることはできない。
文:有丘糺