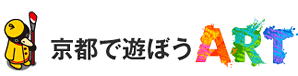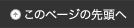- 京都で遊ぼうART
- Report & Review
- 虹の会さんの記事一覧
- 生誕100年記念写真展ロベール・ドアノー@美術館「えき」KYOTO
写真展なんてものに興味はなかったし、ドアノーさんのお名前も知らなかったけれど、ポスターに使われた「増水した側溝、1934年」を見た瞬間にノックアウトされました。 この可愛らしさは何なんだ~、他の写真はどうなんだ~、好奇心を抑えきれず、会場に足を運びました。
占領下のパリを写した初期の作品は、緊迫感あふれるものでした。
空襲警報の鳴る地下鉄の駅で、レジスタンス基地で自家発電する自転車のような装置、 深夜のビラ貼り、バリケードづくり、そして、解放。ドゴール万歳!!
続いて、平和なパリを舞台に撮られた作品は、喜びと愛情にあふれていました。
通りで、川辺で、橋の上で、公園で、広場で、街角で、市場で、お店で、 パリのあらゆるところにいる人たち、キスを交わすカップルたち。 遠景で、近景で、たくさんで、たった一人でとらえられた人たちが、 写真のなかで生き生きと生きていました。
さらにすすむと、子どもたちを映した作品が並んで展示されていました。
つぶれるくらいにガラス窓に鼻を押しつけてこっちを見る女の子、 呼び鈴を押して逃げさるピンポン・ダッシュの男の子たち、 並んでおしっこする男の子たちの後ろ姿とハトのとまった1人の子、 まるでアヒルの行列のように前の子のスモックをつかんで列になって通りを渡る子どもたち。
きりとられたその瞬間の前後の物語を想像せずにはいられない写真が続きます。
自分の写真を「日曜大工の仕事」とたとえることを好み、 「自分は芸術家ではない」と言い続けたというドアノー。
真実を引き出すために、気配を消し、観察し、粘り強く待ったというドアノー。
幸福感と人間愛にあふれた素晴らしい写真展でした。
文責:虹色
関連リンク
ボランティアライター・
ボランティアブロガーの皆様
-
 アカサカさん
アカサカさん -
 AKIさん
AKIさん -
 賀茂茄子さん
賀茂茄子さん -
 azukiさん
azukiさん -
 Nao.Takaさん
Nao.Takaさん -
 chakotakoさん
chakotakoさん -
 chamuさん
chamuさん -
 Chisa Shojiさん
Chisa Shojiさん -
 めぐるさん
めぐるさん -
 無一さん
無一さん -
 まこさん
まこさん -
 ウルトラの母さん
ウルトラの母さん -
 キタムラジュンコさん
キタムラジュンコさん -
 risatoさん
risatoさん -
 はやしまきこさん
はやしまきこさん -
 ナオトさん
ナオトさん -
 Caluさん
Caluさん -
 HIPPOさん
HIPPOさん -
 ひるやまさん
ひるやまさん -
 アキホートンさん
アキホートンさん -
 さくらむくおさん
さくらむくおさん -
 いなこさん
いなこさん -
 かんなさん
かんなさん -
 中里 楓さん
中里 楓さん -
 keicoさん
keicoさん -
 キンタさん
キンタさん -
 きんとよさん
きんとよさん -
 KAさん
KAさん -
 Kohji Oonoさん
Kohji Oonoさん -
 おこめさん
おこめさん -
 たけうまさん
たけうまさん -
 此糸さん
此糸さん -
 licoluiseさん
licoluiseさん -
 まなてぃさん
まなてぃさん -
 アイナエさん
アイナエさん -
 阿月猫さん
阿月猫さん -
 めいさん
めいさん -
 目目沢ミコさん
目目沢ミコさん -
 もりやすみきさん
もりやすみきさん -
 ナミキ・キヨタカさん
ナミキ・キヨタカさん -
 虹の会さん
虹の会さん -
 有丘糺さん
有丘糺さん -
 大石 ゆうさん
大石 ゆうさん -
 岡田 慶子さん
岡田 慶子さん -
 小野寺香奈さん
小野寺香奈さん -
 soraさん
soraさん -
 ぷちりんごさん
ぷちりんごさん -
 sachihoさん
sachihoさん -
 TOSHIさん
TOSHIさん -
 白くま子さん
白くま子さん -
 そらさん
そらさん -
 kotohaさん
kotohaさん -
 柚子さん
柚子さん -
 GYSPY KYOTO !さん
GYSPY KYOTO !さん -
 たまりこさん
たまりこさん -
 tengoku10さん
tengoku10さん -
 sayokoさん
sayokoさん -
 もりのうさまるさん
もりのうさまるさん -
 ツツジさん
ツツジさん -
 梅田たけしさん
梅田たけしさん -
 Watada Mieさん
Watada Mieさん -
 yoshikoさん
yoshikoさん -
 ゆうたんさん
ゆうたんさん -
 ほたるさん
ほたるさん
総合月別アーカイブ
- 2020年3月 (13)
- 2020年2月 (15)
- 2020年1月 (13)
- 2019年12月 (14)
- 2019年11月 (17)
- 2019年10月 (17)
- 2019年9月 (14)
- 2019年8月 (11)
- 2019年7月 (16)
- 2019年6月 (16)
- 2019年5月 (16)
- 2019年4月 (10)
- 2019年3月 (14)
- 2019年2月 (12)
- 2019年1月 (14)
- 2018年12月 (8)
- 2018年11月 (19)
- 2018年10月 (23)
- 2018年9月 (18)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (9)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (6)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (8)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (7)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (5)
- 2017年10月 (7)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (7)
- 2017年2月 (5)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (6)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (9)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (8)
- 2016年6月 (5)
- 2016年5月 (10)
- 2016年4月 (5)
- 2016年3月 (12)
- 2016年2月 (14)
- 2016年1月 (6)
- 2015年12月 (8)
- 2015年11月 (15)
- 2015年10月 (2)
- 2015年9月 (11)
- 2015年8月 (8)
- 2015年7月 (18)
- 2015年6月 (9)
- 2015年5月 (17)
- 2015年4月 (11)
- 2015年3月 (8)
- 2015年2月 (10)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (28)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (12)
- 2014年9月 (12)
- 2014年8月 (22)
- 2014年7月 (15)
- 2014年6月 (27)
- 2014年5月 (42)
- 2014年4月 (20)
- 2014年3月 (13)
- 2014年2月 (20)
- 2014年1月 (21)
- 2013年12月 (46)
- 2013年11月 (27)
- 2013年10月 (21)
- 2013年9月 (27)
- 2013年8月 (34)
- 2013年7月 (21)
- 2013年6月 (15)
- 2013年5月 (32)
- 2013年4月 (42)
- 2013年3月 (27)
- 2013年2月 (12)
- 2013年1月 (14)
- 2012年12月 (9)
- 2012年11月 (11)
- 2012年10月 (6)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (12)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (5)
- 2012年5月 (9)
- 2012年4月 (5)
- 2012年3月 (9)
- 2012年2月 (11)
- 2012年1月 (9)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (13)
- 2011年10月 (10)
- 2011年9月 (8)
- 2011年8月 (13)
- 2011年7月 (10)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (7)
- 2011年4月 (7)
- 2011年3月 (4)
- 2011年2月 (5)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (13)
- 2010年11月 (7)