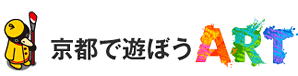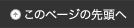- 京都で遊ぼうART
- Report & Review
- chakotakoさんの記事一覧
- 泥象 鈴木治の世界―「使う陶」から「観る陶」、そして「詠む陶」へ―
京都国立近代美術館で開催されている「泥象(でいしょう) 鈴木 治 の世界」を見た。
初期から最晩年までの150点余り。
今回の展覧会の特徴は、鈴木氏の言葉を手がかりとして、活動を読み直すものだという。
「使う陶」から「観る陶」そして「詠む陶」へーこのサブタイトルは、彼の個展での言葉を元にしている。

《泥象》1965年
八木一夫、山田光らと前衛陶芸家集団「走泥社(そうでいしゃ)」を結成したのは1948年。
彼らは、用途を持たない造形を追求した。
揶揄気味に「オブジェ焼き」と呼ばれることに抵抗感を持っていた彼は、それに代わる言葉として「泥像(でいぞう)」を用いた。
古代中国稜墓の副葬品や、彫刻家イサム・ ノグチのテラコッタの作品などに大きな影響を受けた。
土偶や埴輪などが持つダイレクトな土の力と、自由な表現を模索し始める。
轆轤(ろくろ)から離れて、立体形や平面的な作品が生み出された。

《馬》 1977年
彼の作品は主に焼締と青白磁で、色ではなく形の作家と言われている。
中でも動物の造形ー特に馬は繰り返し制作している。
形を抽象化するのではなく、手の内で自分の想像力を形にしていく作業の果てに出来たもの。
「(抽象)よりも(象徴)だ」というのが彼の言葉である。
後に「泥像」から「泥象」と言葉を変えた理由は、森羅万象に目を向ける姿勢の表れである。
雲や風、太陽などをテーマにした作品は、軽やかでどこかユーモラス。

《風の十字路》 1982年
中央の十字が印象的な「風の十字路」
わずかな隙間から吹き抜ける風を感じさせる。

《消えた雲》 1982年
「消えた雲」も、物語の中の一場面のよう。

《掌上泥象百種》 1987年
101種の手のひらに乗る程の作品群「掌上泥象(しょうじょうでいしょう)」は、それぞれ名前がついている。
それらを一つ一つ眺めていると、愉快な気持ちになってくる。
さて、90年代には、彼が言う「詠む陶」を制作する。

《主従出發 - 騎士(左)・従者(右)》 1993年

《晩秋 - 泥象 馬 二十五種ノ内》 1996年
「主従出發(しゅじゅうしゅっぱつ)」や「晩秋」など、イメージの世界を形と色に落とし込み、微妙な陰影を表現している。
どの作品にも、斬新さとイメージの豊かさ、そして詩情がある。
物語を創るのは、あなた方ですよと言われているようだ。
※画像の作品は全て京都国立近代美術館蔵
泥象 鈴木治の世界―「使う陶」から「観る陶」、そして「詠む陶」へ―
ボランティアライター・
ボランティアブロガーの皆様
-
 アカサカさん
アカサカさん -
 AKIさん
AKIさん -
 賀茂茄子さん
賀茂茄子さん -
 azukiさん
azukiさん -
 Nao.Takaさん
Nao.Takaさん -
 chakotakoさん
chakotakoさん -
 chamuさん
chamuさん -
 Chisa Shojiさん
Chisa Shojiさん -
 めぐるさん
めぐるさん -
 無一さん
無一さん -
 まこさん
まこさん -
 ウルトラの母さん
ウルトラの母さん -
 キタムラジュンコさん
キタムラジュンコさん -
 risatoさん
risatoさん -
 はやしまきこさん
はやしまきこさん -
 ナオトさん
ナオトさん -
 Caluさん
Caluさん -
 HIPPOさん
HIPPOさん -
 ひるやまさん
ひるやまさん -
 アキホートンさん
アキホートンさん -
 さくらむくおさん
さくらむくおさん -
 いなこさん
いなこさん -
 かんなさん
かんなさん -
 中里 楓さん
中里 楓さん -
 keicoさん
keicoさん -
 キンタさん
キンタさん -
 きんとよさん
きんとよさん -
 KAさん
KAさん -
 Kohji Oonoさん
Kohji Oonoさん -
 おこめさん
おこめさん -
 たけうまさん
たけうまさん -
 此糸さん
此糸さん -
 licoluiseさん
licoluiseさん -
 まなてぃさん
まなてぃさん -
 アイナエさん
アイナエさん -
 阿月猫さん
阿月猫さん -
 めいさん
めいさん -
 目目沢ミコさん
目目沢ミコさん -
 もりやすみきさん
もりやすみきさん -
 ナミキ・キヨタカさん
ナミキ・キヨタカさん -
 虹の会さん
虹の会さん -
 有丘糺さん
有丘糺さん -
 大石 ゆうさん
大石 ゆうさん -
 岡田 慶子さん
岡田 慶子さん -
 小野寺香奈さん
小野寺香奈さん -
 soraさん
soraさん -
 ぷちりんごさん
ぷちりんごさん -
 sachihoさん
sachihoさん -
 TOSHIさん
TOSHIさん -
 白くま子さん
白くま子さん -
 そらさん
そらさん -
 kotohaさん
kotohaさん -
 柚子さん
柚子さん -
 GYSPY KYOTO !さん
GYSPY KYOTO !さん -
 たまりこさん
たまりこさん -
 tengoku10さん
tengoku10さん -
 sayokoさん
sayokoさん -
 もりのうさまるさん
もりのうさまるさん -
 ツツジさん
ツツジさん -
 梅田たけしさん
梅田たけしさん -
 Watada Mieさん
Watada Mieさん -
 yoshikoさん
yoshikoさん -
 ゆうたんさん
ゆうたんさん -
 ほたるさん
ほたるさん
総合月別アーカイブ
- 2020年3月 (13)
- 2020年2月 (15)
- 2020年1月 (13)
- 2019年12月 (14)
- 2019年11月 (17)
- 2019年10月 (17)
- 2019年9月 (14)
- 2019年8月 (11)
- 2019年7月 (16)
- 2019年6月 (16)
- 2019年5月 (16)
- 2019年4月 (10)
- 2019年3月 (14)
- 2019年2月 (12)
- 2019年1月 (14)
- 2018年12月 (8)
- 2018年11月 (19)
- 2018年10月 (23)
- 2018年9月 (18)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (9)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (6)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (8)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (7)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (5)
- 2017年10月 (7)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (7)
- 2017年2月 (5)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (6)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (9)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (8)
- 2016年6月 (5)
- 2016年5月 (10)
- 2016年4月 (5)
- 2016年3月 (12)
- 2016年2月 (14)
- 2016年1月 (6)
- 2015年12月 (8)
- 2015年11月 (15)
- 2015年10月 (2)
- 2015年9月 (11)
- 2015年8月 (8)
- 2015年7月 (18)
- 2015年6月 (9)
- 2015年5月 (17)
- 2015年4月 (11)
- 2015年3月 (8)
- 2015年2月 (10)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (28)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (12)
- 2014年9月 (12)
- 2014年8月 (22)
- 2014年7月 (15)
- 2014年6月 (27)
- 2014年5月 (42)
- 2014年4月 (20)
- 2014年3月 (13)
- 2014年2月 (20)
- 2014年1月 (21)
- 2013年12月 (46)
- 2013年11月 (27)
- 2013年10月 (21)
- 2013年9月 (27)
- 2013年8月 (34)
- 2013年7月 (21)
- 2013年6月 (15)
- 2013年5月 (32)
- 2013年4月 (42)
- 2013年3月 (27)
- 2013年2月 (12)
- 2013年1月 (14)
- 2012年12月 (9)
- 2012年11月 (11)
- 2012年10月 (6)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (12)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (5)
- 2012年5月 (9)
- 2012年4月 (5)
- 2012年3月 (9)
- 2012年2月 (11)
- 2012年1月 (9)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (13)
- 2011年10月 (10)
- 2011年9月 (8)
- 2011年8月 (13)
- 2011年7月 (10)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (7)
- 2011年4月 (7)
- 2011年3月 (4)
- 2011年2月 (5)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (13)
- 2010年11月 (7)