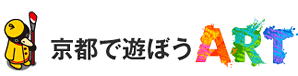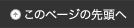- 京都で遊ぼうART
- Report & Review
- ナミキ・キヨタカさんの記事一覧
- それほどまでにパリ、パリ、パリ...「ロニスの見つめたパリの自由 WILLY RONIS 展」(何必館・京都現代美術館)

『バスティーユの恋人』(1957)
フランスの写真家と言われて思い浮かぶのはブレッソン、ドアノー、ブラッサイぐらい。
あっ、イヨネスコと...。
不覚にもウイリー・ロニスという人は知らなかった。
アンリ・カルティエ・ブレッソンは「マグナム」をキャパらと立ち上げ、雑誌の依頼で世界中を激写したという行動力と実行力にあふれた、また終戦までレジスタンス運動に加わるという明快な志向性を示したカメラマンでジャーナリスティックな視点を持った人という印象が強い。
一方「市役所前のキス」という作品で有名なロベール・ドアノーは
被写体たちの奥底にあるペーソスを浮かび上がらせ、
結果的に決して大袈裟ではないドラマチックな空気を画面に醸し出す。
そこにあるのはささやかなペーソスとユーモア。
いずれもフランスを代表するヒューマニズム写真家であり、
ウイリー・ロニスもその一人だと言う。
三人に共通しているのは(もちろんブラッサイにも)
パリという街に、そこに住む人々に魅せられたこと。
ここに展示されているオリジナルプリント60点を一つひとつ見てみると
写真が好きな人、写真を撮ることを趣味にしている人、
仕事にしている人問わず、
こんなロケーション、シチュエーションに満ち満ちている
"過去"のパリにワープしたい気持ちにかられるだろう。
苦い辛い歴史の果てにある庶民の姿、
ことに「生きること」への執着と喜びを
被写体である彼らは実に素直に表し、また写真家はその一瞬を捕まえる。
限りなく豊穣な街、パリ。
常々思うのだが、撮るという行為に先んじて現象が起こるわけで
これを逃さないということ、そのこと自体が写真家の写真家たる天分ではないか、
そんな風にも思う。
パリに行ったこともない僕が現在も過去も比較しようもないが
確かなことは、このモノクロで切り取られた光景に
奥行きの深い、僕たちに色彩の想像をさせないほどに新鮮な
街の、人の吐息を感じるのだ。
そしてカメラというハードウエアに任せなければ
どこまでいっても成立しない写真家の成分は
しかし1%の機能と99%の感覚でできているのではないか。
「カメラは道具、道具は考えない。
この道具の背後には私の眼があり、頭脳がある。
シャッターを押す時、この頭脳が選択する。
写真家の行為は心の中のことである。
客観性はない。」
と語るロニスが見つけた、いや"発見"する影は
人の機微を実によく描写している。
こういう展覧会に出会うたびに写真には門外漢の僕でも
モノクロ写真の洗礼を全身で浴びることになる。
会場を出た瞬間に目もくらむほどの
無秩序な色彩が飛び込んで来ると
もう一度、深遠なそして美しく物の、人の表情をとどめ置く
黒白(こくびゃく)の世界へ戻りたくなるのである。
文責:den 編集:京都で遊ぼうART
関連リンク
ボランティアライター・
ボランティアブロガーの皆様
-
 アカサカさん
アカサカさん -
 AKIさん
AKIさん -
 賀茂茄子さん
賀茂茄子さん -
 azukiさん
azukiさん -
 Nao.Takaさん
Nao.Takaさん -
 chakotakoさん
chakotakoさん -
 chamuさん
chamuさん -
 Chisa Shojiさん
Chisa Shojiさん -
 めぐるさん
めぐるさん -
 無一さん
無一さん -
 まこさん
まこさん -
 ウルトラの母さん
ウルトラの母さん -
 キタムラジュンコさん
キタムラジュンコさん -
 risatoさん
risatoさん -
 はやしまきこさん
はやしまきこさん -
 ナオトさん
ナオトさん -
 Caluさん
Caluさん -
 HIPPOさん
HIPPOさん -
 ひるやまさん
ひるやまさん -
 アキホートンさん
アキホートンさん -
 さくらむくおさん
さくらむくおさん -
 いなこさん
いなこさん -
 かんなさん
かんなさん -
 中里 楓さん
中里 楓さん -
 keicoさん
keicoさん -
 キンタさん
キンタさん -
 きんとよさん
きんとよさん -
 KAさん
KAさん -
 Kohji Oonoさん
Kohji Oonoさん -
 おこめさん
おこめさん -
 たけうまさん
たけうまさん -
 此糸さん
此糸さん -
 licoluiseさん
licoluiseさん -
 まなてぃさん
まなてぃさん -
 アイナエさん
アイナエさん -
 阿月猫さん
阿月猫さん -
 めいさん
めいさん -
 目目沢ミコさん
目目沢ミコさん -
 もりやすみきさん
もりやすみきさん -
 ナミキ・キヨタカさん
ナミキ・キヨタカさん -
 虹の会さん
虹の会さん -
 有丘糺さん
有丘糺さん -
 大石 ゆうさん
大石 ゆうさん -
 岡田 慶子さん
岡田 慶子さん -
 小野寺香奈さん
小野寺香奈さん -
 soraさん
soraさん -
 ぷちりんごさん
ぷちりんごさん -
 sachihoさん
sachihoさん -
 TOSHIさん
TOSHIさん -
 白くま子さん
白くま子さん -
 そらさん
そらさん -
 kotohaさん
kotohaさん -
 柚子さん
柚子さん -
 GYSPY KYOTO !さん
GYSPY KYOTO !さん -
 たまりこさん
たまりこさん -
 tengoku10さん
tengoku10さん -
 sayokoさん
sayokoさん -
 もりのうさまるさん
もりのうさまるさん -
 ツツジさん
ツツジさん -
 梅田たけしさん
梅田たけしさん -
 Watada Mieさん
Watada Mieさん -
 yoshikoさん
yoshikoさん -
 ゆうたんさん
ゆうたんさん -
 ほたるさん
ほたるさん
総合月別アーカイブ
- 2020年3月 (13)
- 2020年2月 (15)
- 2020年1月 (13)
- 2019年12月 (14)
- 2019年11月 (17)
- 2019年10月 (17)
- 2019年9月 (14)
- 2019年8月 (11)
- 2019年7月 (16)
- 2019年6月 (16)
- 2019年5月 (16)
- 2019年4月 (10)
- 2019年3月 (14)
- 2019年2月 (12)
- 2019年1月 (14)
- 2018年12月 (8)
- 2018年11月 (19)
- 2018年10月 (23)
- 2018年9月 (18)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (9)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (6)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (8)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (7)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (5)
- 2017年10月 (7)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (7)
- 2017年2月 (5)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (6)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (9)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (8)
- 2016年6月 (5)
- 2016年5月 (10)
- 2016年4月 (5)
- 2016年3月 (12)
- 2016年2月 (14)
- 2016年1月 (6)
- 2015年12月 (8)
- 2015年11月 (15)
- 2015年10月 (2)
- 2015年9月 (11)
- 2015年8月 (8)
- 2015年7月 (18)
- 2015年6月 (9)
- 2015年5月 (17)
- 2015年4月 (11)
- 2015年3月 (8)
- 2015年2月 (10)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (28)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (12)
- 2014年9月 (12)
- 2014年8月 (22)
- 2014年7月 (15)
- 2014年6月 (27)
- 2014年5月 (42)
- 2014年4月 (20)
- 2014年3月 (13)
- 2014年2月 (20)
- 2014年1月 (21)
- 2013年12月 (46)
- 2013年11月 (27)
- 2013年10月 (21)
- 2013年9月 (27)
- 2013年8月 (34)
- 2013年7月 (21)
- 2013年6月 (15)
- 2013年5月 (32)
- 2013年4月 (42)
- 2013年3月 (27)
- 2013年2月 (12)
- 2013年1月 (14)
- 2012年12月 (9)
- 2012年11月 (11)
- 2012年10月 (6)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (12)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (5)
- 2012年5月 (9)
- 2012年4月 (5)
- 2012年3月 (9)
- 2012年2月 (11)
- 2012年1月 (9)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (13)
- 2011年10月 (10)
- 2011年9月 (8)
- 2011年8月 (13)
- 2011年7月 (10)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (7)
- 2011年4月 (7)
- 2011年3月 (4)
- 2011年2月 (5)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (13)
- 2010年11月 (7)