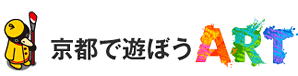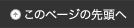- 京都で遊ぼうART
- Report & Review
- ナミキ・キヨタカさんの記事一覧
- がぷり四つ、ほとばしる抽象...「伊吹 拓 展 あるままにひかる」(neutron kyoto)
撫でたり、さすったり、つねったり、舐めたり、つまんだりすることだけではない。
この確認はどこまでも触感だけに頼ったもので
それ以上でも以下でもなく、そこに"或る"ことを確かめているだけだ。
以前ダンスのワークショップで
二人一組になって一人がもう一人の腕を取り、
とは言ってもそこに他意を感じさせないほどに滑らかにそっと握り、
そのまま静かに前後に動くというのをやった。
腕を取られている側も同じように動く。
どこかで力が入ると途端に相手の腕は反応する。
その反応とは逃避だったり、不自然な同調だったりする。
そこでは相手の腕の皮一枚を意識して
相手の触感と同化する、つまり相殺するということ。
なぜか、この抽象画を見てそんなことを思い出した。
僕たちの周りはなんらかの気配で溢れている。
気配だけで成立しているような気さえする。
実は目に見えているものなど意味が無いほどに...。
ギャラリーの壁にかけられた300号もの大きさの作品から発せられるものは
圧巻とか壮観とかではなくて、
作家の言う"色彩を引き出そう"とする並々ならぬ強固な意志。
体積やサイズに圧倒されるだけではない作家の決意のようなものを感じる。
それこそがカンバスから放たれる気配ではないだろうか。
僕はこの抽象の中に首まで、肩まで、腰まで、いや全身を浸かる。
neutronの石橋さんがコメントで書かれているように
作家の絵画に描かれているのは矛盾と共感の塊としての「存在」。
人と人との関係性もまた相反する矛盾と共感を抱えつつ成立する。
そして人を語る時も結局はかなり抽象的な表現に着地する。
僕にとっての抽象画、という言い方で括るつもりはないが
"理解し難いもの"への様々な反応もまた絵を観るということに他ならない。
食わず嫌いはいけないとかでもなく、
「描くひと」は絶えず、自己と支持体、人生観と画法、洗練と野蛮、
常識と間違いを対比させ、にらみ合いながら
自己表現の一環として絵を選ぶわけだから、
せめても一途な情感のほとばしりを浴びようではないか。
それにしても画材を媒介しながら色彩とうまくつき合っていくのは
想像を超えた骨の折れる仕事だろうと思う。
チューブからひねり出した色が色なのではなく、
ここに置きたい色こそが作家にとっての色。
でも色は中々出てくれない。
で、作家は必死になって色出しをするのだ。
色彩、その軌跡、情感の発露、そうやって形を立ち上らせる絵という所産...。
一昨年に第一子が誕生されたという作家自身の心の有り様は
神秘の命、成長、そして安寧や平安を願う気持ちを
新しい基軸にして展開していくのだろう。
"絵を描くこと"を通じて...。
文責:den 編集:京都で遊ぼうART
関連リンク
伊吹 拓 展 『あるままにひかる』neutron kyoto
denさんのブログ「シッタカブリアンの午睡」
★「京都で遊ぼうART」に参加してみませんか?★
京都で遊ぼうARTでは展覧会や施設の感想や、京都のアート情報の紹介を随時募集しています。
展覧会や施設に行ってみた方、生の感想を是非お寄せ下さい!
また、アートイベントや展覧会の開催情報など、アーティストさんや主催者さんなどからの掲載依頼も随時受け付け中です!
→ボランティアライターに関する詳細はこちら
→お問合せについてはこちら
京都で遊ぼうARTでは展覧会や施設の感想や、京都のアート情報の紹介を随時募集しています。
展覧会や施設に行ってみた方、生の感想を是非お寄せ下さい!
また、アートイベントや展覧会の開催情報など、アーティストさんや主催者さんなどからの掲載依頼も随時受け付け中です!
→ボランティアライターに関する詳細はこちら
→お問合せについてはこちら
ボランティアライター・
ボランティアブロガーの皆様
-
 アカサカさん
アカサカさん -
 AKIさん
AKIさん -
 賀茂茄子さん
賀茂茄子さん -
 azukiさん
azukiさん -
 Nao.Takaさん
Nao.Takaさん -
 chakotakoさん
chakotakoさん -
 chamuさん
chamuさん -
 Chisa Shojiさん
Chisa Shojiさん -
 めぐるさん
めぐるさん -
 無一さん
無一さん -
 まこさん
まこさん -
 ウルトラの母さん
ウルトラの母さん -
 キタムラジュンコさん
キタムラジュンコさん -
 risatoさん
risatoさん -
 はやしまきこさん
はやしまきこさん -
 ナオトさん
ナオトさん -
 Caluさん
Caluさん -
 HIPPOさん
HIPPOさん -
 ひるやまさん
ひるやまさん -
 アキホートンさん
アキホートンさん -
 さくらむくおさん
さくらむくおさん -
 いなこさん
いなこさん -
 かんなさん
かんなさん -
 中里 楓さん
中里 楓さん -
 keicoさん
keicoさん -
 キンタさん
キンタさん -
 きんとよさん
きんとよさん -
 KAさん
KAさん -
 Kohji Oonoさん
Kohji Oonoさん -
 おこめさん
おこめさん -
 たけうまさん
たけうまさん -
 此糸さん
此糸さん -
 licoluiseさん
licoluiseさん -
 まなてぃさん
まなてぃさん -
 アイナエさん
アイナエさん -
 阿月猫さん
阿月猫さん -
 めいさん
めいさん -
 目目沢ミコさん
目目沢ミコさん -
 もりやすみきさん
もりやすみきさん -
 ナミキ・キヨタカさん
ナミキ・キヨタカさん -
 虹の会さん
虹の会さん -
 有丘糺さん
有丘糺さん -
 大石 ゆうさん
大石 ゆうさん -
 岡田 慶子さん
岡田 慶子さん -
 小野寺香奈さん
小野寺香奈さん -
 soraさん
soraさん -
 ぷちりんごさん
ぷちりんごさん -
 sachihoさん
sachihoさん -
 TOSHIさん
TOSHIさん -
 白くま子さん
白くま子さん -
 そらさん
そらさん -
 kotohaさん
kotohaさん -
 柚子さん
柚子さん -
 GYSPY KYOTO !さん
GYSPY KYOTO !さん -
 たまりこさん
たまりこさん -
 tengoku10さん
tengoku10さん -
 sayokoさん
sayokoさん -
 もりのうさまるさん
もりのうさまるさん -
 ツツジさん
ツツジさん -
 梅田たけしさん
梅田たけしさん -
 Watada Mieさん
Watada Mieさん -
 yoshikoさん
yoshikoさん -
 ゆうたんさん
ゆうたんさん -
 ほたるさん
ほたるさん
総合月別アーカイブ
- 2020年3月 (13)
- 2020年2月 (15)
- 2020年1月 (13)
- 2019年12月 (14)
- 2019年11月 (17)
- 2019年10月 (17)
- 2019年9月 (14)
- 2019年8月 (11)
- 2019年7月 (16)
- 2019年6月 (16)
- 2019年5月 (16)
- 2019年4月 (10)
- 2019年3月 (14)
- 2019年2月 (12)
- 2019年1月 (14)
- 2018年12月 (8)
- 2018年11月 (19)
- 2018年10月 (23)
- 2018年9月 (18)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (9)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (6)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (8)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (7)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (5)
- 2017年10月 (7)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (7)
- 2017年2月 (5)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (6)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (9)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (8)
- 2016年6月 (5)
- 2016年5月 (10)
- 2016年4月 (5)
- 2016年3月 (12)
- 2016年2月 (14)
- 2016年1月 (6)
- 2015年12月 (8)
- 2015年11月 (15)
- 2015年10月 (2)
- 2015年9月 (11)
- 2015年8月 (8)
- 2015年7月 (18)
- 2015年6月 (9)
- 2015年5月 (17)
- 2015年4月 (11)
- 2015年3月 (8)
- 2015年2月 (10)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (28)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (12)
- 2014年9月 (12)
- 2014年8月 (22)
- 2014年7月 (15)
- 2014年6月 (27)
- 2014年5月 (42)
- 2014年4月 (20)
- 2014年3月 (13)
- 2014年2月 (20)
- 2014年1月 (21)
- 2013年12月 (46)
- 2013年11月 (27)
- 2013年10月 (21)
- 2013年9月 (27)
- 2013年8月 (34)
- 2013年7月 (21)
- 2013年6月 (15)
- 2013年5月 (32)
- 2013年4月 (42)
- 2013年3月 (27)
- 2013年2月 (12)
- 2013年1月 (14)
- 2012年12月 (9)
- 2012年11月 (11)
- 2012年10月 (6)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (12)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (5)
- 2012年5月 (9)
- 2012年4月 (5)
- 2012年3月 (9)
- 2012年2月 (11)
- 2012年1月 (9)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (13)
- 2011年10月 (10)
- 2011年9月 (8)
- 2011年8月 (13)
- 2011年7月 (10)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (7)
- 2011年4月 (7)
- 2011年3月 (4)
- 2011年2月 (5)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (13)
- 2010年11月 (7)