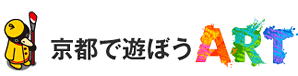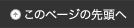- 京都で遊ぼうART
- Report & Review
- ナミキ・キヨタカさんの記事一覧
- ファンキーなアニマルたちがお待ちかね...(「 MEET THE ANIMALS! ホームルーム 三沢 厚彦 /京都芸術センター)
Meet The Animals-ホームルーム(4/10-5/22)
TDLのファンは何よりもあの着ぐるみに異常なほどの親愛を抱く。
中身で汗にまみれている肉体はすでに問題ではない。
見た目、外側である。
つまるところ、僕たちは自分の持つありったけの想像力でもって
彼らを外側から受け入れ、善人説の極みとも言える寛容さをもって接する。
勿論相手も同じ。
相手の立場で考えればホスピタリティ以外の何物でもない。
彼らの剽軽でメリハリのあるゼスチャアはその絶対条件になるし、
何よりも“生き者としての対象”を感じさせる“訓練”は欠かせない。
ここにある三沢さんが作り出す動物たちは
当然ながら微動だにしない。
じっとなどしない着ぐるみと比べたら真逆なのだが
僕たちは彼らが今にも喋るんじゃないか、動くんじゃないかと
愉快な心地にゆったりと浸ることになる。
リアルとは何だろう。
例えば原寸大の像を作ろうとする時、作家が
「原寸大の動物彫刻 ≒ リアリティ」と考えても
何ひとつおかしくも間違ってもいないが、
それは本物そっくり!という(高いハードルだが)結果で収束する。
観客はそこから先へ進めなくなる。
それほどにリアルならば…。
僕が言う「しゃべり出しそう」という感覚はその先のものだ。
それも僕のわかる言葉で。
着ぐるみが“進んで”キャラクターになろうとする動機も効果も
当然承知の上であれだけもてはやされるのは
特にTDLの場合などは「Welcome」意識の極みだと言ってもいい。
「来てくれたんだね!」という例のあれだ。
ここの、ノミの削り後の質感がそのまま皮膚感となっている
数々の動物たちは実に無口なのだが
ここに来ることを同じように待っているのだ。
観客と対峙した時に彼らの声は発せられ、彼らの体温が上がるのだ。
これもクスの木に宿る木霊のしわざかも知れない。
じぃーっと向かい合っていると不思議な気分になる。
この作品は一つひとつとしっかり向き合いながら
心で触れながらじっくりと見て欲しい。
彼らからほのかに漂う木の香りと微かな塗料の匂いとのブレンドは
なぜか僕に遠い昔を思い出させた。
彼らに一番近づきたければ正面に立って、挨拶すればいい。
シロクマや犬やバク、鹿や猫、フクロウにいたるまで
正面の顔の表情は格別である。
見た事もない(しかもバカデカ!)ペガサスさえも
背中の羽がいつ羽ばたいてもおかしくないほどに
観客の心との距離間に親愛の情を育んでいく。
そして作品はどれも立派過ぎるほどに
たくましく自己紹介をしている。
このファンキーなデフォルメされた
動物たちにぜひ出会ってください。
命に満ちた“肉付き”のよさをアナタの目で。
文責:den 編集:京都で遊ぼうART
→ denさんのブログへ
関連リンク
Meet The Animals-ホームルーム
京都芸術センター
京都で遊ぼうARTでは展覧会や施設の感想や、京都のアート情報の紹介を随時募集しています。
展覧会や施設に行ってみた方、生の感想を是非お寄せ下さい!
また、アートイベントや展覧会の開催情報など、アーティストさんや主催者さんなどからの掲載依頼も随時受け付け中です!
→ボランティアライターに関する詳細はこちら
→お問合せについてはこちら
ボランティアライター・
ボランティアブロガーの皆様
-
 アカサカさん
アカサカさん -
 AKIさん
AKIさん -
 賀茂茄子さん
賀茂茄子さん -
 azukiさん
azukiさん -
 Nao.Takaさん
Nao.Takaさん -
 chakotakoさん
chakotakoさん -
 chamuさん
chamuさん -
 Chisa Shojiさん
Chisa Shojiさん -
 めぐるさん
めぐるさん -
 無一さん
無一さん -
 まこさん
まこさん -
 ウルトラの母さん
ウルトラの母さん -
 キタムラジュンコさん
キタムラジュンコさん -
 risatoさん
risatoさん -
 はやしまきこさん
はやしまきこさん -
 ナオトさん
ナオトさん -
 Caluさん
Caluさん -
 HIPPOさん
HIPPOさん -
 ひるやまさん
ひるやまさん -
 アキホートンさん
アキホートンさん -
 さくらむくおさん
さくらむくおさん -
 いなこさん
いなこさん -
 かんなさん
かんなさん -
 中里 楓さん
中里 楓さん -
 keicoさん
keicoさん -
 キンタさん
キンタさん -
 きんとよさん
きんとよさん -
 KAさん
KAさん -
 Kohji Oonoさん
Kohji Oonoさん -
 おこめさん
おこめさん -
 たけうまさん
たけうまさん -
 此糸さん
此糸さん -
 licoluiseさん
licoluiseさん -
 まなてぃさん
まなてぃさん -
 アイナエさん
アイナエさん -
 阿月猫さん
阿月猫さん -
 めいさん
めいさん -
 目目沢ミコさん
目目沢ミコさん -
 もりやすみきさん
もりやすみきさん -
 ナミキ・キヨタカさん
ナミキ・キヨタカさん -
 虹の会さん
虹の会さん -
 有丘糺さん
有丘糺さん -
 大石 ゆうさん
大石 ゆうさん -
 岡田 慶子さん
岡田 慶子さん -
 小野寺香奈さん
小野寺香奈さん -
 soraさん
soraさん -
 ぷちりんごさん
ぷちりんごさん -
 sachihoさん
sachihoさん -
 TOSHIさん
TOSHIさん -
 白くま子さん
白くま子さん -
 そらさん
そらさん -
 kotohaさん
kotohaさん -
 柚子さん
柚子さん -
 GYSPY KYOTO !さん
GYSPY KYOTO !さん -
 たまりこさん
たまりこさん -
 tengoku10さん
tengoku10さん -
 sayokoさん
sayokoさん -
 もりのうさまるさん
もりのうさまるさん -
 ツツジさん
ツツジさん -
 梅田たけしさん
梅田たけしさん -
 Watada Mieさん
Watada Mieさん -
 yoshikoさん
yoshikoさん -
 ゆうたんさん
ゆうたんさん -
 ほたるさん
ほたるさん
総合月別アーカイブ
- 2020年3月 (13)
- 2020年2月 (15)
- 2020年1月 (13)
- 2019年12月 (14)
- 2019年11月 (17)
- 2019年10月 (17)
- 2019年9月 (14)
- 2019年8月 (11)
- 2019年7月 (16)
- 2019年6月 (16)
- 2019年5月 (16)
- 2019年4月 (10)
- 2019年3月 (14)
- 2019年2月 (12)
- 2019年1月 (14)
- 2018年12月 (8)
- 2018年11月 (19)
- 2018年10月 (23)
- 2018年9月 (18)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (9)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (6)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (8)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (7)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (5)
- 2017年10月 (7)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (7)
- 2017年2月 (5)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (6)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (9)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (8)
- 2016年6月 (5)
- 2016年5月 (10)
- 2016年4月 (5)
- 2016年3月 (12)
- 2016年2月 (14)
- 2016年1月 (6)
- 2015年12月 (8)
- 2015年11月 (15)
- 2015年10月 (2)
- 2015年9月 (11)
- 2015年8月 (8)
- 2015年7月 (18)
- 2015年6月 (9)
- 2015年5月 (17)
- 2015年4月 (11)
- 2015年3月 (8)
- 2015年2月 (10)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (28)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (12)
- 2014年9月 (12)
- 2014年8月 (22)
- 2014年7月 (15)
- 2014年6月 (27)
- 2014年5月 (42)
- 2014年4月 (20)
- 2014年3月 (13)
- 2014年2月 (20)
- 2014年1月 (21)
- 2013年12月 (46)
- 2013年11月 (27)
- 2013年10月 (21)
- 2013年9月 (27)
- 2013年8月 (34)
- 2013年7月 (21)
- 2013年6月 (15)
- 2013年5月 (32)
- 2013年4月 (42)
- 2013年3月 (27)
- 2013年2月 (12)
- 2013年1月 (14)
- 2012年12月 (9)
- 2012年11月 (11)
- 2012年10月 (6)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (12)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (5)
- 2012年5月 (9)
- 2012年4月 (5)
- 2012年3月 (9)
- 2012年2月 (11)
- 2012年1月 (9)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (13)
- 2011年10月 (10)
- 2011年9月 (8)
- 2011年8月 (13)
- 2011年7月 (10)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (7)
- 2011年4月 (7)
- 2011年3月 (4)
- 2011年2月 (5)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (13)
- 2010年11月 (7)