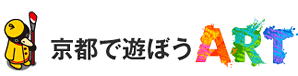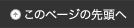- 京都で遊ぼうART
- Report & Review
- ナミキ・キヨタカさんの記事一覧
- 「ごちそうさま」の少し前の風景...「sweet memory おとぎ話の王子でも 」展(京都芸術センター)(4)
 瓜生祐子≪birthday cake≫
瓜生祐子≪birthday cake≫2010年(アクリル、鉛筆、綿布、木製パネル)
「Sweet Memory」での最後のレビューは瓜生さん。
同期開催として旧作新作織り交ぜて、三条通りの別のギャラリー(Gallery PARC「Plate journey 瓜生祐子展」)でも発表されている。
以前 neutron kyoto での個展を見逃していただけに同時に二つも観られてなんだか瓜生スペシャルな感じだ。
瓜生さんの絵は遠目からだと色彩のトーンが均一だ。
観る側に過度な情報を与えまいとしているかのようである。
まず木製パネルにアクリル絵具で色を塗った後に、全体を薄い布で覆い、その布の上から鉛筆で輪郭を描き起こしている。
食卓の上の風景。
デコレーションケーキ、幕の内弁当、ピザ、ビスケット、クスクス…
ああ、皿の上の食べ物を風景に見立てて…と得心するのは簡単なのだが、
風景画に欠かせない遠近感も、エッジもここではあえて削ぎおとしている。
彩度を抑揚のないものにしているのも
観客にイマジネーションを喚起させて欲しい
という瓜生さんの計らいであろうと想像する。
食べ物を風景画のように描いた作品という括りでは
多分不完全な紹介の仕方になると思う。
観客はこの絵のどこに入り込むか、どこから観るかを楽しむ。
これは作者が楽しみながら描き、尚“描き切らず”にいることを含めての作品だと思う。
猶予を残すというのは作家としてはしんどい。
もっと立体的に描いたらとか、もっとヴィヴィッドに、とかは誰でも考える。
しかしその絵は飾った瞬間に完結してしまうだろう。
はっきり言えば、これらの絵の中に“器用さ”といった
画家としての武器はそのなりを潜めている。
瓜生さんはこれらの絵のキャプションを
観る人がそれぞれにつけたらいい、とそんな風に思えてくる。
観客が入り込む余地を残しつつ、
観客の口の中が甘くなったり、酸っぱくなったりすることを望んでいるのかも。
どことなくヨーロッパのどこかの国の絵本の挿絵のようなテイスト。
やはり綿布の効果は絶大だったようだ。
当たり前の日常にみるカウンターの上の、テーブルの上の食べ物について
視覚が占める時間はつかの間のうちに去っていく。
目的はあくまで食べることであって、観ることではない。
だからこうして絵にとどめておく。
これらの絵に共通しているのはいずれも
スプーンを、フォークを、箸を入れた後である。
食べ進むうちに皿の上の物体は確かにだらしないものになる。
しかしそこには優先順位や
食べ方によるその人の現在の心持ちというものが反映される。
話はそれるが、粗相のないように食べようと腐心する最初の
恋人とのディナーや、育ちをどうのこうのと指摘されるのを心配して緊張を強いられ、かえって肉を飛ばしてしまったりと、
こと食べる事に関するエピソードは誰にでもあるものだ。
本来は抽象画を描かれていた瓜生さんが
カレーを食べていた時にライスは山に、ルーは海に見えてくる。
ライスのガケが崩れ、島ができたり、池になったりと…。
そして最後は皿だけになる。
「ごちそうさまでした」
これが制作の発端であるから、みんな安心するのだ。
そうして得たインスピレーションを
毒々しく、また可笑しみをもって表現とするのも美術だし、
こうして儚く、淡く(しかもファンシーに陥らない寸止め)
“ゆっくりと平和に”観られる作品というのも、やはり心を平安にする。
文責:den 編集:京都で遊ぼうART
→ケーキと権威...「sweet memory―おとぎ話の王子でも 」展(京都芸術センター)(1)
→涙腺の共感を琥珀に閉じ込める...「sweet memory おとぎ話の王子でも 」展(京都芸術センター)(2)
→食べ物で遊んではダメ、って言われました?...「sweet memory おとぎ話の王子でも」展(京都芸術センター)(3)
関連リンク
ボランティアライター・
ボランティアブロガーの皆様
-
 アカサカさん
アカサカさん -
 AKIさん
AKIさん -
 賀茂茄子さん
賀茂茄子さん -
 azukiさん
azukiさん -
 Nao.Takaさん
Nao.Takaさん -
 chakotakoさん
chakotakoさん -
 chamuさん
chamuさん -
 Chisa Shojiさん
Chisa Shojiさん -
 めぐるさん
めぐるさん -
 無一さん
無一さん -
 まこさん
まこさん -
 ウルトラの母さん
ウルトラの母さん -
 キタムラジュンコさん
キタムラジュンコさん -
 risatoさん
risatoさん -
 はやしまきこさん
はやしまきこさん -
 ナオトさん
ナオトさん -
 Caluさん
Caluさん -
 HIPPOさん
HIPPOさん -
 ひるやまさん
ひるやまさん -
 アキホートンさん
アキホートンさん -
 さくらむくおさん
さくらむくおさん -
 いなこさん
いなこさん -
 かんなさん
かんなさん -
 中里 楓さん
中里 楓さん -
 keicoさん
keicoさん -
 キンタさん
キンタさん -
 きんとよさん
きんとよさん -
 KAさん
KAさん -
 Kohji Oonoさん
Kohji Oonoさん -
 おこめさん
おこめさん -
 たけうまさん
たけうまさん -
 此糸さん
此糸さん -
 licoluiseさん
licoluiseさん -
 まなてぃさん
まなてぃさん -
 アイナエさん
アイナエさん -
 阿月猫さん
阿月猫さん -
 めいさん
めいさん -
 目目沢ミコさん
目目沢ミコさん -
 もりやすみきさん
もりやすみきさん -
 ナミキ・キヨタカさん
ナミキ・キヨタカさん -
 虹の会さん
虹の会さん -
 有丘糺さん
有丘糺さん -
 大石 ゆうさん
大石 ゆうさん -
 岡田 慶子さん
岡田 慶子さん -
 小野寺香奈さん
小野寺香奈さん -
 soraさん
soraさん -
 ぷちりんごさん
ぷちりんごさん -
 sachihoさん
sachihoさん -
 TOSHIさん
TOSHIさん -
 白くま子さん
白くま子さん -
 そらさん
そらさん -
 kotohaさん
kotohaさん -
 柚子さん
柚子さん -
 GYSPY KYOTO !さん
GYSPY KYOTO !さん -
 たまりこさん
たまりこさん -
 tengoku10さん
tengoku10さん -
 sayokoさん
sayokoさん -
 もりのうさまるさん
もりのうさまるさん -
 ツツジさん
ツツジさん -
 梅田たけしさん
梅田たけしさん -
 Watada Mieさん
Watada Mieさん -
 yoshikoさん
yoshikoさん -
 ゆうたんさん
ゆうたんさん -
 ほたるさん
ほたるさん
総合月別アーカイブ
- 2020年3月 (13)
- 2020年2月 (15)
- 2020年1月 (13)
- 2019年12月 (14)
- 2019年11月 (17)
- 2019年10月 (17)
- 2019年9月 (14)
- 2019年8月 (11)
- 2019年7月 (16)
- 2019年6月 (16)
- 2019年5月 (16)
- 2019年4月 (10)
- 2019年3月 (14)
- 2019年2月 (12)
- 2019年1月 (14)
- 2018年12月 (8)
- 2018年11月 (19)
- 2018年10月 (23)
- 2018年9月 (18)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (9)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (6)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (8)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (7)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (5)
- 2017年10月 (7)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (7)
- 2017年2月 (5)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (6)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (9)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (8)
- 2016年6月 (5)
- 2016年5月 (10)
- 2016年4月 (5)
- 2016年3月 (12)
- 2016年2月 (14)
- 2016年1月 (6)
- 2015年12月 (8)
- 2015年11月 (15)
- 2015年10月 (2)
- 2015年9月 (11)
- 2015年8月 (8)
- 2015年7月 (18)
- 2015年6月 (9)
- 2015年5月 (17)
- 2015年4月 (11)
- 2015年3月 (8)
- 2015年2月 (10)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (28)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (12)
- 2014年9月 (12)
- 2014年8月 (22)
- 2014年7月 (15)
- 2014年6月 (27)
- 2014年5月 (42)
- 2014年4月 (20)
- 2014年3月 (13)
- 2014年2月 (20)
- 2014年1月 (21)
- 2013年12月 (46)
- 2013年11月 (27)
- 2013年10月 (21)
- 2013年9月 (27)
- 2013年8月 (34)
- 2013年7月 (21)
- 2013年6月 (15)
- 2013年5月 (32)
- 2013年4月 (42)
- 2013年3月 (27)
- 2013年2月 (12)
- 2013年1月 (14)
- 2012年12月 (9)
- 2012年11月 (11)
- 2012年10月 (6)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (12)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (5)
- 2012年5月 (9)
- 2012年4月 (5)
- 2012年3月 (9)
- 2012年2月 (11)
- 2012年1月 (9)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (13)
- 2011年10月 (10)
- 2011年9月 (8)
- 2011年8月 (13)
- 2011年7月 (10)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (7)
- 2011年4月 (7)
- 2011年3月 (4)
- 2011年2月 (5)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (13)
- 2010年11月 (7)