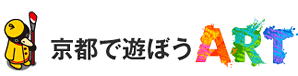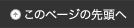- 京都で遊ぼうART
- Report & Review
- licoluiseさんの記事一覧
- 国画会90年 孤高の画家 渡辺貞一 私の信仰は描くことです
美術館「えき」KYOTOで開催中の「渡辺貞一展」のオープニングに出かけてきました。
皆さんはこの画家をご存知だったでしょうか?私は初めて目にし、耳にした洋画家です。

洋画家・渡辺貞一(1917-1981)は、青森市に生まれました。幼い頃より絵を描くのは上手だったそうですが、画家を志すきっかけは長兄の突然の死でした。「人間は死ぬものだ。生きているうちに好きな絵を描こう」と決めたそうです。青森師範学校の図画専科でデッサン・油絵を習い、18歳で上京して川端画学校で学びました。20代半ばの1941(昭和16年)には第16回国展に出品、初入選するも、喀血で倒れて療養のため帰郷を余儀なくされます。このころの顔色の悪い、不安げな自画像が残っていました。ギャラリー椿で開催された遺作展にある年表には「結核を患い療養のため八甲田山中にこもる」とあります。
翌年には再び上京して海軍要員に応募し南ボルネオに出征します。画家を志した身から上京した先にあったのが出征だったのか、「出征」が先にあったのか。戦地でも生と死の境を彷徨います。1946年無事復員し、キリスト教に入信します。
彼の生涯の前半は「生と死」と見つめる日々であったことでしょう。「生と死」と「青森原風景」は、画家・渡辺貞一の作品に通奏低音の様に流れています。
渡辺貞一は、「国画会」を活動の中心として、個展を開催して制作発表を行ってきました。住まいも東京で、京都とはご縁があまりありません。展覧会サブタイトルにある「国画会90年」の「国画会」が、もともとは京都の日本画団体として始まった「国画創作協会」だったことくらいです。何故に?京都で回顧展が開催されることとなったかといいますと、京都在住のコレクター・中井昌美氏がドーンと渡辺貞一作品を青森県七戸町に寄贈されたことによります。今回の展覧会もその寄贈作品が中心となっています。
寒々しい故郷青森の風景の中の人物の点景は、ルオーを思い起こしました。朝日ジャーナルの表紙となった第36回国画会展出品作《囚われた船》を前にして「もしや…」と感じました。キャプションを読むとやはりそうで、これは国立西洋美術館の常設にあるピュヴィ・ド・シャヴァンヌ《貧しき漁夫》からインスピレーションを得て描いた作品です。深い信仰心も内包しているようです。鳥、月、野の花、少女、川原などをモチーフに、渡辺独自のマチエールに惹きこまれます。厳しい精神性をも感じ、幻想的でもある作品ではないでしょうか。コレクター・中井昌美氏は、現在アートに些か疑問をも抱いておられるようで、そこへの問題提起でもある展覧会開催となっているかもしれません。
画面を作り込んでいた渡辺は、それほど老いてはいない晩年には、体力の衰えからそれまでの様に油彩が描けなくなったとありました。それも一因の水墨画で、キリスト者ではありましたが、水墨画に没頭し仏画も描いています。彼の描く水墨画は清々しくもありました。
展覧会では、渡辺家が所蔵する関連資料も展示され、写真などからは気が強かったと言われる渡辺の優しさも伝わってきました。
八戸市では、新美術館の建設が進められています。新美術館の所蔵となればこれだけまとまって洋画家・渡辺貞一の作品を京都で観る機会はなく、今回は貴重な機会となっています。
ボランティアライター・
ボランティアブロガーの皆様
-
 アカサカさん
アカサカさん -
 AKIさん
AKIさん -
 賀茂茄子さん
賀茂茄子さん -
 azukiさん
azukiさん -
 Nao.Takaさん
Nao.Takaさん -
 chakotakoさん
chakotakoさん -
 chamuさん
chamuさん -
 Chisa Shojiさん
Chisa Shojiさん -
 めぐるさん
めぐるさん -
 無一さん
無一さん -
 まこさん
まこさん -
 ウルトラの母さん
ウルトラの母さん -
 キタムラジュンコさん
キタムラジュンコさん -
 risatoさん
risatoさん -
 はやしまきこさん
はやしまきこさん -
 ナオトさん
ナオトさん -
 Caluさん
Caluさん -
 HIPPOさん
HIPPOさん -
 ひるやまさん
ひるやまさん -
 アキホートンさん
アキホートンさん -
 さくらむくおさん
さくらむくおさん -
 いなこさん
いなこさん -
 かんなさん
かんなさん -
 中里 楓さん
中里 楓さん -
 keicoさん
keicoさん -
 キンタさん
キンタさん -
 きんとよさん
きんとよさん -
 KAさん
KAさん -
 Kohji Oonoさん
Kohji Oonoさん -
 おこめさん
おこめさん -
 たけうまさん
たけうまさん -
 此糸さん
此糸さん -
 licoluiseさん
licoluiseさん -
 まなてぃさん
まなてぃさん -
 アイナエさん
アイナエさん -
 阿月猫さん
阿月猫さん -
 めいさん
めいさん -
 目目沢ミコさん
目目沢ミコさん -
 もりやすみきさん
もりやすみきさん -
 ナミキ・キヨタカさん
ナミキ・キヨタカさん -
 虹の会さん
虹の会さん -
 有丘糺さん
有丘糺さん -
 大石 ゆうさん
大石 ゆうさん -
 岡田 慶子さん
岡田 慶子さん -
 小野寺香奈さん
小野寺香奈さん -
 soraさん
soraさん -
 ぷちりんごさん
ぷちりんごさん -
 sachihoさん
sachihoさん -
 TOSHIさん
TOSHIさん -
 白くま子さん
白くま子さん -
 そらさん
そらさん -
 kotohaさん
kotohaさん -
 柚子さん
柚子さん -
 GYSPY KYOTO !さん
GYSPY KYOTO !さん -
 たまりこさん
たまりこさん -
 tengoku10さん
tengoku10さん -
 sayokoさん
sayokoさん -
 もりのうさまるさん
もりのうさまるさん -
 ツツジさん
ツツジさん -
 梅田たけしさん
梅田たけしさん -
 Watada Mieさん
Watada Mieさん -
 yoshikoさん
yoshikoさん -
 ゆうたんさん
ゆうたんさん -
 ほたるさん
ほたるさん
総合月別アーカイブ
- 2020年3月 (13)
- 2020年2月 (15)
- 2020年1月 (13)
- 2019年12月 (14)
- 2019年11月 (17)
- 2019年10月 (17)
- 2019年9月 (14)
- 2019年8月 (11)
- 2019年7月 (16)
- 2019年6月 (16)
- 2019年5月 (16)
- 2019年4月 (10)
- 2019年3月 (14)
- 2019年2月 (12)
- 2019年1月 (14)
- 2018年12月 (8)
- 2018年11月 (19)
- 2018年10月 (23)
- 2018年9月 (18)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (9)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (6)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (8)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (7)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (5)
- 2017年10月 (7)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (7)
- 2017年2月 (5)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (6)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (9)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (8)
- 2016年6月 (5)
- 2016年5月 (10)
- 2016年4月 (5)
- 2016年3月 (12)
- 2016年2月 (14)
- 2016年1月 (6)
- 2015年12月 (8)
- 2015年11月 (15)
- 2015年10月 (2)
- 2015年9月 (11)
- 2015年8月 (8)
- 2015年7月 (18)
- 2015年6月 (9)
- 2015年5月 (17)
- 2015年4月 (11)
- 2015年3月 (8)
- 2015年2月 (10)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (28)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (12)
- 2014年9月 (12)
- 2014年8月 (22)
- 2014年7月 (15)
- 2014年6月 (27)
- 2014年5月 (42)
- 2014年4月 (20)
- 2014年3月 (13)
- 2014年2月 (20)
- 2014年1月 (21)
- 2013年12月 (46)
- 2013年11月 (27)
- 2013年10月 (21)
- 2013年9月 (27)
- 2013年8月 (34)
- 2013年7月 (21)
- 2013年6月 (15)
- 2013年5月 (32)
- 2013年4月 (42)
- 2013年3月 (27)
- 2013年2月 (12)
- 2013年1月 (14)
- 2012年12月 (9)
- 2012年11月 (11)
- 2012年10月 (6)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (12)
- 2012年7月 (10)
- 2012年6月 (5)
- 2012年5月 (9)
- 2012年4月 (5)
- 2012年3月 (9)
- 2012年2月 (11)
- 2012年1月 (9)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (13)
- 2011年10月 (10)
- 2011年9月 (8)
- 2011年8月 (13)
- 2011年7月 (10)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (7)
- 2011年4月 (7)
- 2011年3月 (4)
- 2011年2月 (5)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (13)
- 2010年11月 (7)